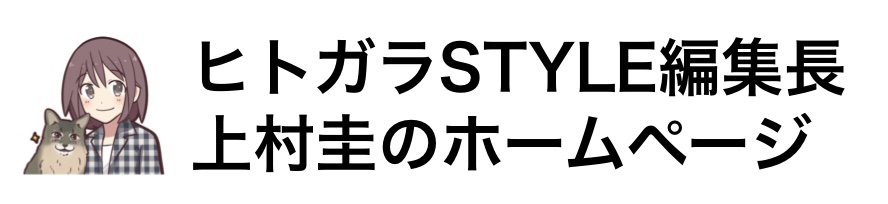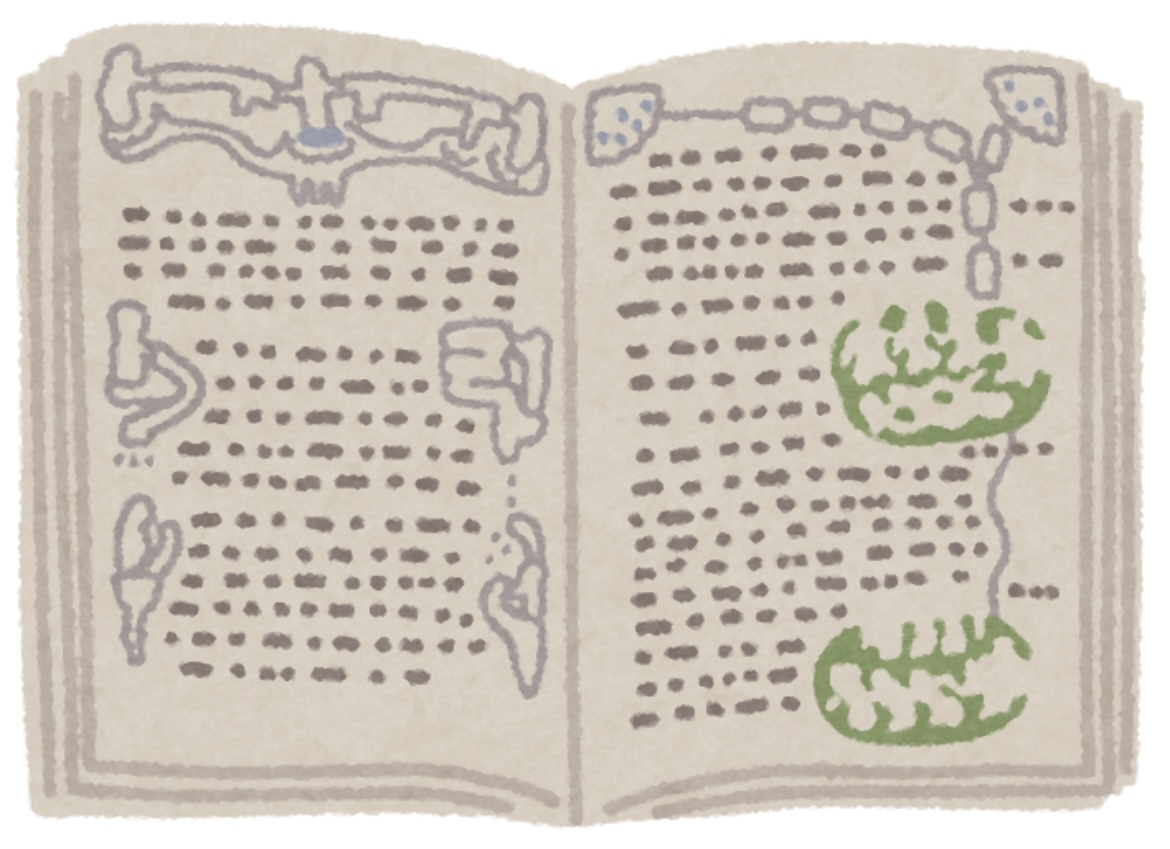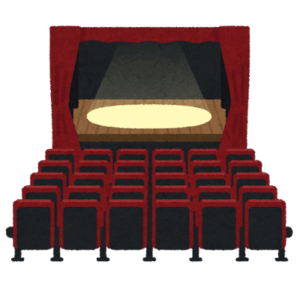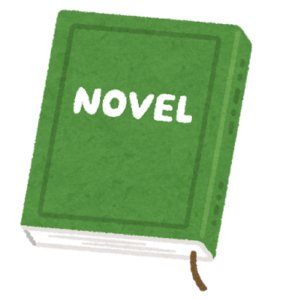本を読むときに
「これは大事!🤨」
と思った部分をメモしておく。
これは多くの人がやっていることだと思いますし、私もとてもいい習慣だと思っています。
読みながらメモをとると、ただ眺めていたら流れてしまう言葉も、深く考えながら読めますよね。
だから、学びを定着させたいならメモ読書はすごく有効だと思います。
でも最近、私はあることに気づいたんです。
それは「メモには弱点もあるのかもしれない」ということ。
名著と最近の本の“似ているポイント”
たとえば自己啓発やビジネス書など、同じジャンルの本をいくつも読むとします。
すると、名著と呼ばれる昔の本と、最近出た新しい本とで、「重要ポイント」がけっこう似ていることに気づくんです。
これはある意味当然のこと。
最近の本の著者は、すでに世の中にある複数の本や名著の知識をベースにしつつ、自分の経験や考えを付け加えて書いているからです。
もちろん最近の骨太の本は、かなり違う角度から書かれたものもあります。
でも「エッセンス」だけで比べると、どの本も似てきてしまうんですよね。
名著と普通の本の違いはどこにあるの?
ここで私が思ったのが、「じゃあ名著と普通の本の違いってどこにあるの?」という疑問です。
たとえば、本の中に「重要ポイント①」と「重要ポイント②」があったとします。
読んでいるときは「ここが大事だ!」と思ってメモを取りますよね。
でも、最近ふと気づいたんです。
本当に大事なのは、重要ポイント以外の部分なんじゃないか?と。
例えば「①から②へとつなぐ文脈」だったり、重要ポイントに至るまでの過程であったり。
そこにこそ、著者の深い思考や、読み手がじっくり味わうべき濃厚な部分があるのではと思っています。
名著と呼ばれる本が、ただの“ありきたりなポイント集”に終わらないのは、まさにその「間」や「過程」にあるからだと思います。
『人を動かす』の例
有名な名著に、デール・カーネギーの『人を動かす』があります。
これを読んだことがある人ならわかると思うのですが、内容だけをポイントで並べると、
相手を尊重する
批判しない
認める
……といった、ものすごくシンプルで、むしろ
「当たり前やん😳」
と思えることばかりです。
なのでもし本文を読まずに重要ポイントだけ読んだら(各章の最後にまとまっています)、
「名著とはいったい・・・・・・
うごごご!!🫠」
ってなるかもしれません。
でも、この本が“名著”とされるのは、単に「相手を尊重しましょう」とか書かれているからではありません。
そのポイントに至るまでのストーリーや、エピソード、背景の積み重ね。
そういう部分を読むことで、読者は深く納得し、心が動かされるんです。
もしポイントだけをメモしてしまったら、この名著の濃厚さはごっそり抜け落ちてしまうんですよね。
超訳や要約がちょっと微妙に感じる理由
同じ意味で、最近よく見かける「超訳」や「要約」も、私はちょっと微妙に感じています。
もちろん短時間でざっくり内容を知るには役立ちます。
でもやっぱり、重要ポイントだけを抜き出すと、どの本も同じに見えてしまう。
その本だけが持っている厚みや独自性は、要約ではなかなか伝わらないんです。
付箋読書も同じ落とし穴がある
ちなみに、付箋を貼る読書法もありますよね。
「これは大事!🤨」
と思ったらペタッと貼っておく。
これももちろん効果的なんですが、メモと同じように「付箋を貼った部分だけ」を見返すと、本の全体像が抜け落ちてしまいます。
だからもし復習するなら、「付箋の箇所を中心にしつつ、それ以外の部分も読み直す」のが理想だと思っています。
付箋やメモはあくまで“入り口”であって、“ゴール”ではないんですよね。
メモや付箋は深く読むための“手段”
とはいえ、私はメモや付箋を否定しているわけではありません。
むしろ、それを取ること自体はとても良いことだと思っています。
なぜなら、メモや付箋を残す瞬間は
「これってどういう意味なんだろう?🤔」
と深く考えながら読むことになるからです。
これはただ流し読みするより、はるかに学びが定着します。
なので、読書中にメモや付箋を使うことはこれからもおすすめしたい習慣です。
復習するなら「もう一度読む」
ただし、復習という観点ではどうでしょうか。
正直なところ、私は「メモや付箋を見返すよりも、その本をもう一度読む方がいい」と思うようになりました。
もちろん時間が許せば、の話です。
同じ本を2度3度読むのは、なかなか大変ですからね。
でも、本当に濃厚な部分は「ポイントとポイントの間」に隠れている。
だから2回目、3回目に読んだときこそ、初めて読んだ時には見逃していたその“間”に気づけることがあるんです。
そしてその瞬間にこそ、その本が「名著」と呼ばれる理由を実感できるのだと思います。
まとめ:大事なのは「重要ポイントじゃない部分」
というわけでここまでお話ししてきたことをまとめると、
・重要ポイントをメモする読書はとても良い
・でも「名著」と「普通の本」の違いは、ポイントそのものより“間”にある
・付箋やメモは効果的だが、それだけに頼ると本質を逃す
・復習するときは、メモや付箋よりも本をもう一度読む方が、濃厚な部分に気づける
ということです。
メモ読書や付箋読書をしながらも、できれば「もう一回読む」ことを忘れない。
それがきっと、本当の意味での学びにつながるのではないかと思います。
重要じゃない部分が重要。
これはあくまで私の個人的な意見ですが、私はそう感じています。
……知らんけど🫠
※この記事は上村圭が「読書法」について思ってる事を主張しただけの記事です。「勉強法」はまた別です。